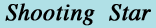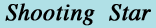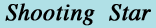今朝、学生寮の廊下で女子から一通の封筒を無言で差し出された。
その後、彼女はなかなか話さず、俯いてばかりで顔を上げても真っ赤になって、また下を向いての繰り返しをしていた。わずか離れた柱の所に友達だろう、二人の女子が小声で“頑張れ”“早く言って”等言っていた。それでも口を開くことなく俯く彼女。
『好きです!これ、読んで下さい!』
勇気を振り絞っての告白である。彼女の顔は、最初より更に赤みを増していた。
『断る』
スコールは即答し、その場を去ろうとした。
しかし、告白したこと少し勇気がもてたのか、再び回り込み彼女はまた封筒を差し出した。
『読んでくれるだけでもいいんです!』
『他人の気持ちを押し付けられるのは、嫌なんだ。他の奴に言ってくれ』
完全な拒絶。
彼女は俯き、封筒と共に差し出していた腕をもどす。そして手の中で、受け取られなかったそれを握りしめた。足元に水滴が、一つ二つと落ちる。
状況を察した友達が駆け寄ってきた。
スコールは、用は終わったとばかりに歩き出す。しばらくして後ろから“何様のつもりっ!”とか“最低な男ねっ!”と罵声が聞こえてきたが、彼が振り返ることはなかった。