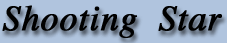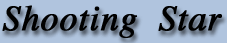プロとして通用する高い戦闘能力を備えた人物の養成を行う私立の兵士養成学校。通称『ガーデン』。
現在、3校あるガーデンの中心的存在である、ここ『バラムガーデン』は、自由で開放的な雰囲気に包まれている。校内での行動や服装は、生徒の自主性にまかされているし、24時間利用可能な訓練施設があるため、バトルへの関心は高い。生徒が独自に結成したサークル活動も活発で、“自由奔放”という言葉か教育方針と捉えられてもおかしくない学園である。
その1F、寮や食堂のある生活の場の廊下を1人の女性が歩いている。
彼女の名は、キスティス・トュリープ。
10歳でガーデンに入学し、15歳で試験資格を得ると同時に最年少でSeeDに合格。また、17歳の若さで教員の資格までも取得した超エリートである。その才色兼備ぶりから、男女を問わずに熱狂的な崇拝者は多い。『トュリープFC』が組織される程で、授業用のイミテーションの眼鏡が、知的な女性を常に演出している。
キスティスにとって日常と化している憧れの眼差しが、今日も向けられていた。声を掛ければ穏やかな表情で挨拶を交わしてくれる。言葉を返された生徒は、その表情と眼鏡の下の優しい眼差しに酔いしれていた。
しかし穏やかに見える表情の裏は、焦り、急ぎで一杯だった。
彼女の歩く先は、自然と道が出来ていくので幸いな事なのだが、これから向かう先はこうはいかない。それにこうして悠長に歩いている間にも、目的の人物は、予測不可能な行動をする者だ。
歩く速度が徐々に速くなっていた。