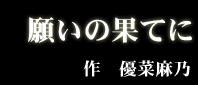
それは月の明るい夜にしか出来ないおまじない。
ガラスの器に水を張り、好きな花かもしくはその花のはなびらを浮かべて一晩月光の元に置いておく。
そうすると月の女神と星の精霊が願いを聞き届けてくれるという小さな小さな白魔術。
いつの間にか年頃の少女たちの間で広まるようになったその小さな魔法は、幾世代もの間密やかに伝えられてきたもの。
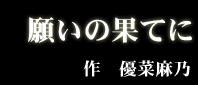 |
|
それは月の明るい夜にしか出来ないおまじない。 ガラスの器に水を張り、好きな花かもしくはその花のはなびらを浮かべて一晩月光の元に置いておく。 そうすると月の女神と星の精霊が願いを聞き届けてくれるという小さな小さな白魔術。 いつの間にか年頃の少女たちの間で広まるようになったその小さな魔法は、幾世代もの間密やかに伝えられてきたもの。 |
| 今宵もまた、少女たちは小さな魔法に願いと想いを託す。 |
| かたりという小さな音にスタイナーは背後を振り返った。
夜目にもその意匠の細かさがわかるレースのカーテンを開けてテラスに出てきたのはショールを羽織ったガーネットだった。夜になって少し強くなってきた風に彼女の髪がふわりと舞い上がり、薄手の夜着の 裾が揺らめく。髪を押さえてほんの少し笑った彼女に、忠実な王宮騎士は咄嗟には反応できず直立不動の体勢のまま一礼する。主君たる人の夜着をまとった姿を彼のような人間が見るのは言うまでもなくもってのほかである。 しかし、気候のよい時節にはこうして窓を開けたまま彼女は幾夜でも過ごしてしまう。そんなガーネットの部屋のテラスの前で寝ずの番をするのは、スタイナーとしては他の者になど任せてはおけない重要な 任務の一つなのだ。その任務が終わるのは、彼にとっても馴染みの深い人物があてのない旅から戻ってくる時である。 「いつもご苦労様。でも、多分今夜はもう帰ってこないと思うから、あなたも屋敷に戻ってちょうだい」 無意識のうちに主語を抜かした言葉でも、十分スタイナーには意味が通じた。 「しかし、窓を開けたままというのは無用心極まりないことです。自分ならば少々の徹夜など平気ですので…」 「最近そうやって全然屋敷に帰っていないそうね。ローズマリーに顔を忘れられてはいけないのではなくて?」 苦笑と微笑ましさを半々にこめた主君の笑みと言葉に、スタイナーはそれとこれとは話が別です、と言いかけて更に追い討ちをかけられてしまう。 「私の警護をするよりも、ローズの面倒を見てあげて欲しいのだけど。ベアトリクスだって一人では心細いでしょうに。気のきく乳母がいるとは言っていたけれど、父親の役目も重要でしょう?」 大丈夫、あなたが帰ったらちゃんと窓も閉めますから、と言われてしまってスタイナーは一気に劣勢に追い込まれた。 ローズマリー――愛称ローズ――はつい数ヶ月前に生まれたスタイナーとベアトリクスの娘である。母親似の愛らしい女児は女王からローズマリーという名を賜り、周囲の大人たちから溢れんばかりの祝福を受けてすくすくと成長している。 赤子がある程度成長するまではいったん職を退いて屋敷にいるベアトリクスも、初めての子育てについては以前の職務よりも難しいことと時折言いつつも、生まれて間もない赤子の愛らしさに目を細めながら 穏やかな日々を送っているらしい。 「ご命令とあらば、おっしゃる通りにいたしますが…」 「では命令します。アデルバート・スタイナー、ローズマリーがあなたの顔を忘れてしまう前に急いでお帰りなさい」 愛娘のことを出されるとかたなしになってしまうスタイナーのこと、ましてや女王当人からそのようなことを言われては命令を実行するしか手立てはない。 しかし、スタイナーはほんの一瞬躊躇した後にこう言った。 「陛下。…何があっても、自分は陛下のお味方です」 それが何を意味するのかガーネットも十分わかっていた。 ジタンが仮にも一国の女王の居室に夜陰に乗じて滑り込めるのは、スタイナーとベアトリクスの助力あってこそという面もある。水ももらさぬ構えの警備に、ほんの一点針の穴のような隙間をあけたその警備の穴を潜り抜けてジタンは城に帰ってくる。 それは、見て見ぬふりをするという彼らなりの精一杯の心遣いであった。 身分違いの恋と言われようと、女王にあるまじきことと言われようと、彼女は自分にとって大切な人が誰であるか身をもってわかっていた。そしてその大切な者との恋は、こぞって祝福されるようなものでは ないのだということも。 懸命に真面目な顔をして、でもどこか嬉しそうな気配を隠しきれないまま一礼して足早に立ち去ろうとしたスタイナーの背中に、再度女王の声がかけられた。甲冑の音も騒々しく振り返ったスタイナーの目に、テラスの階段を二、三段慌てて駆け下りたらしいガーネットが笑いかける。 「ベアトリクスに、落ち着いたらまたローズの顔を見せに来てちょうだいと伝えてくれる?」 「はっ!きっと、その…妻も、喜びます」 妻帯して早幾年かが経っているにも関わらず、妻という言葉を口にする時スタイナーはいまだに口ごもってしまう。そのスタイナーに、お願いね、ともう一度念を押してガーネットの細い背が夜風に揺れるカ ーテンの向こうに消えた。 その窓が閉まるのを確認した彼が立ち去ってからしばらく、そっと窓が開けられたことを彼はとうとう知る余地もなかった。 |
| 風が出てきたので少し迷ったのだが、昼間のうちに思いついたことをどうしてもやりたかったので、ガーネットはスタイナーが立ち去ったのを見計らってなるべく窓を静かに開けた。
そして、かねてから用意していたそれを少しおずおずとしながらテラスの床の上に置く。 それは、小さなガラスの器に水を張って、小さな白い花を浮かべたもの。 いつからそのおまじない――小さな白魔術――が広まったのかわからなくなるほど、その小さな儀式は密やかに伝えられ、明るい月夜にはどこかでそっと年頃の少女たちが行っていることだった。 願いをこめた好きな花をガラスの器に浮かべて一晩月光に当てれば月の女神と星の精霊がその願いをかなえてくれるというそのおまじないを、ふと昼間思い出したのはジタンがいない日が長く続いたせいだろ うか。 好きな花はそれこそ季節ごとに数多くあったけれど、特にその花々を選んだ理由にはここ最近の物思いがあったせいかもしれない。 選んだのは、かすみ草とジャスミンの白い小さな花。 伝え聞いたそれらの花の花言葉を思い出して、ガーネットは窓辺に座り込んだままふとため息をついた。 この小さな白魔術は、よくある言い伝え通り他の人に見られてしまうとかなう願いもかなわなくなってしまうという。何故なのか彼女自身もよくはわからないのだが、どうしても今夜おまじないを実行したい 気分になったのだ。 夕刻、西の空が貴婦人のあでやかな夜会服の裾のような色に染まりつつある中、蒼い月が昇ってきたのを見たせいだろうか?それとも、随分長いこと彼の姿を見ていないせいで感傷的な気持ちになっていたせ いだろうか? 夕闇がせまる中、女官たちに見つからないようにそっとテラスから庭園に降りて目当ての花を急いで取ってきた頃にはもう月が高く昇っていた。 ローズのことを話題にしてスタイナーに引き取るように言ったのも勿論彼が家に帰ってないせいもあったが、小さな一人だけの儀式に気がつかれたくなかったからだ。しかし、立ち去っていくスタイナーの背 中を部屋の中から見送った時、自分で自分の体を抱きしめたのは何故だったのだろう。他ならぬ彼女自身が帰るようにと言ったのに、いざ家族の待つ家に帰っていく彼を見た時に言いようのない気持ちになったのは何故だろう。 そして、白く小さなかすみ草とひときわ香りの強いジャスミンの花を摘んできたのは…何故なのだろう。 好きな花ならいくらでも他にあるのだ。それこそ温室で丹精こめて育てられている淡い色合いのミニバラや小ぶりの蘭の花でもよかったのだ。華やかな印象のものでないのなら、ひっそりと咲く桔梗の花もい いだろう。 でも、目にとめて選んだのはこの白くて小さな花々だった。 器に水をはり花の部分だけ丁寧に指先で摘んで水面に浮かべている時、かすみ草の花を浮かべるのには躊躇しなかったのに、ジャスミンの花を手にした時一瞬手が止まった。そしていつの間にかかすみ草で覆 われてしまいそうになっていた水面にほんの一、二輪、ジャスミンの花を落とした。 テラスに置いたガラスの器が銀の月光を音もなくはじいて光のかけらをこぼしている。その様子を窓の内側からじっと見て、ガーネットは窓ガラスに自分の額を押しつけるようにしてうつむき軽く目を閉じた。 何もジャスミンなんて選ぶことなかったのよ。かすみ草だけで十分じゃないの。 そう思った時、目を閉じたままながらもふと影が落ちるのがわかってガーネットは目を開けた。月がかげったのかと思ったその瞬間、その影が窓ガラスのすぐ向こうで人の形を取っているのが見えた。 息をのんでほんの少し顔をあげた時、窓ガラス越しに額が重なるようにコツンと相手が自分の額をガラスに押しつけた。 「――ただいま」 窓ガラス越しの声は、どこか不思議そうな響きを伴って彼女の耳に滑り込んできた。 |
 |
|
とっさに声の出ないガーネットにおやという表情をした後に、ジタンは窓ガラスの向こうから鍵の所を軽く叩いてきた。開けてくれという仕草にガーネットが大げさなほどの音をたてて鍵をはずした時、ジタ ンは足下のガラスの器を見て呟いた。 「これって、おまじないとかそういう種類のものか?…まてよ、こういうのって他の人間が見たら願い事がかなわないとか言うよなあ?うわ、俺変な時に帰ってきちまったのか」 ガーネットが説明するよりも早く、独り合点ながら事を飲み込んでしまうジタンは開けてもらった窓から部屋に入る前に真剣な表情でこう言った。 「あのさ、かなわなかったらまずいから、俺に出来る願い事なら代わりにかなえるよ。何お願いしてたんだ?」 目を見開くようにしてその言葉を聞いていたガーネットは、数瞬遅れた後に彼が旅の途中で一番見たいと思っていた笑顔になった。 「ううん、もういいのよ。半分はかなったもの。でも、今日は普段より早い時間だったのね、おかえりなさい」 笑顔になりつつもふとこぼしてしまったたった一つの言葉にジタンがちょっと眉をあげて尋ね返す。 「半分?」 あ、と口元を押さえて黙り込んでしまうガーネットをしげしげと見た後、彼は俯いてしまう彼女の顔を少しかがみこむようにして覗き込む。 「とすると、そのかなった半分っていうのは俺に何か関係あるわけだ」 ますます俯くガーネットの顔を覗き込みながら、ジタンはわざと疑問符つきの言葉を口にしていく。 「なんか今日のガーネットおかしいよなあ。たまに起きてる時間に帰ってくると抱きついてくれるのに今日はそれもないし…あんまり、嬉しくなかったとか?」 思わず顔をあげたガーネットはその長い髪が揺れるくらいの勢いで首を横に振った。 「そんなこと、あるわけないじゃない。ただ、帰ってくると思ってなかったからすごくびっくりして、びっくりしすぎたから…」 やっぱりちょっと離れすぎてたかな、とジタンが頭をかくような仕草をした。それは、彼が何か照れまじりにごまかすような時の仕草。そして少しかがむような姿勢になると、彼女の瞳を正面からのぞき込む。 「その願い事のかなった半分って…」 俺?と聞くかのように人差し指で自分を指す彼に、更に頬に朱の色を浮かべることで彼女は言葉ではない返事を返す。 「じゃあ、残りの半分も俺がらみだって考えた方が自然だよな。なら、俺がかなえられることなんじゃないのか?」 嬉しそうなジタンの笑顔を見ているうちに、ついさっきまでのあの感情を思い出してガーネットはいたたまれなくなる。かすみ草であふれんばかりの水面に一つ二つとジャスミンの花を落としたその時の気持 ちは、独りよがりすぎて口に出せるようなものではなかったから。 「…そういうところ、あんまり好きじゃないぞ」 ふいに変わった話題と彼の口調に心臓を冷たい手で掴まれた気がしてガーネットは思わずどきりとして彼を見上げる。ふと気がつくと、出会った頃より伸びた背のせいでかがみこんだ姿勢を正した彼の視線と は随分高さが違う。 「なんかどこかで遠慮してる時がたまにあるんだよな。まあそりゃ、願い事なんて俺がかなえられるのかどうかなんてわからないんだけど…」 「願い事だからとか、そういうことではなくて」 反射的に答えた言葉に、ジタンがかすかに笑う。 言わないですむのなら言わないままでいようと思ったのに、彼の言葉一つで言わされてしまう、いや、言いたくなってしまう自分にとっくにガーネットも気がついている。 「だって、勝手すぎるんですもの。周りの皆に助けてもらって、今のままで十分幸せなはずなのに、まだもっともっとって欲しがっているの」 彼の蒼い瞳が二三度瞬きを繰り返し、言葉を十分に知らない小さな子供のようにそう言ったガーネットを見る。考えるより先に言葉にしてしまって自分でも混乱しているらしく、何かを探しているかのような 少し不安な表情の彼女に、再度視線を合わせたジタンは彼女にしか聞こえない程度の小さな声で囁く。 「何が勝手で、何か欲しいのかなんて言ってみないとわからないだろう?」 それがあのおまじないの願いなら尚更だし、と彼はあの出会った日から変わらない人なつっこい笑みを浮かべた。 あの出会った日から、彼の笑顔と言葉にかたくなだった気持ちをどれほど包み込んでもらっただろう。あの時は今よりもずっと心も考えも幼い部分があったが、共有した時間はきっと何にも代え難いもの。そ して、今もまた同じ時間を共有していることを感謝すべきなのに。 「…なんで、そんなことを思ったのかもよくわからないのだけど」 「うん、それで?」 「早く帰ってきてくれないかしらって思っていたら、急にあのおまじないを思い出してどうしてもしたくなって、だから、夕方花を摘んで…」 そこでジタンはテラスの大理石の床の上にあるガラスの器を振り返った。ガラス戸の枠に手をついてかがみこむとその器をのぞき込み、少し首をひねるとこう彼女に尋ねた。 「花に何か意味があるのか?さっきぱっと見ただけの時は白い花が一種類なのかと思ったんだけど、今見たら別の花も混じってるよなあ」 いっそ無邪気と言ってもいいほどのあっけなさで一番隠したかったことを言い当てられて、ガーネットは必死に探していた言葉がするりと逃げてしまうのを感じていた。またうつむいてしまいそうになる彼女 の頬を大きな手がそっと包み込む。 「やっぱり花に意味があるんだ」 ――ああ、もうきっとだめだわ。 久しぶりに触れた彼の温かさに心に絡まっていた糸がゆっくりほどけていくのを感じながら、ガーネットは頬に触れている彼の手に自然と白い小さな手を重ねた。 「好きな花ならなんでもいいの。でも、花言葉の意味を知った上でだと願いもかないやすいって教えてもらったから」 で、その花言葉は?と視線で聞いてくるジタンの瞳にうかされるようにガーネットは呟く。 いつの間にか、二人の距離は吐息が交わるくらいになっている。 「一つの花でも幾つかある場合もあるんだけど…かすみ草が“幸せ”で…」 「そっちは多い方の花?」 「ええ、そう。少ない方のジャスミンの花言葉は」 視線をはずそうと思ってもはずせない。 胸を直接うつように絶え間なく早い鼓動を刻む心臓の音を聞かれてしまうほどではないかと思った直後に、ガーネットの淡紅色の唇からその言葉がこぼれ落ちる。 「“あなたは私のもの”だって、聞いたから」 小さな水面を覆いつくすように、あふれるような“幸せ”を感じているはずなのに、心のどこかでもっと側にいて欲しいと思っている。ただ彼女の側にいるだけでは何も出来ないからと世界を旅し、そして見 聞きしたことを彼女に伝えるジタンの気持ちをわかっていながら、それでもジャスミンの花を摘み取っていた。 心の奥底にしまっておこうとしていた気持ちを口にした途端、涙がにじむのがわかった。 それは、一番自分勝手で一番醜くて、そして一番素直な気持ち。 彼を縛りつけるようなことはしたくない、それは彼らしくあることを否定することだから、と思ってきた。けれどもそれをとうとう口にしてしまった自分に怒りたいのか悲しいのか区別がつきにくくなってし まった時、まるで小さな子供をなだめるように彼女の体を抱きしめたジタンの手がゆっくりとガーネットの細い背を撫でながらこう言った。 「それなら、かなえられるな」 |
 
|
| 「じゃ、そこに座って」
ジタンの言葉に戸惑うガーネットは彼に軽く肩を押されてそのままそこに座り込んだ。やわらかな薄絹の夜着の裾が絨毯の上にふわりと花のように広がったが、普段なら裾に気を遣うガーネットも突然のこと にそれすら忘れていた。 「目、閉じて」 「え?」 「いいから、目閉じて。いいって言うまで開けるなよ」 楽しげな口調でそう繰り返すジタンに小首を傾げたが、ガーネットは素直に目を軽く閉じた。だから、彼女は知らない。ガーネットが目を閉じた途端、ジタンが神妙な表情になったことを。 聞こえてくるのは何か布のようなものが触れあう音だけ。その紐をほどくような音から、彼が旅の間に持ち歩いている荷を開けているのだろうかと見当はついた。しかし、次に聞こえてきた音に彼女は耳を一 層そばだてた。 それは彼女がとても聞き慣れている音だった。確かに、その優しい音は絹ずれの音。それも軽く薄い極上の絹だけがたてる繊細な音。 「…ジタン?」 目を閉じたまま思わずそう話しかけた時、何かがふわりと頭上に舞い降りた。髪に触れる優しくやわらかな感触に目を閉じたまま不思議に思ったのが表情に出たのか、ジタンがかすかに笑う気配を感じる。 「いいよ、開けても」 ゆっくりと目を開けたのは、そのジタンの声に微妙な緊張の色を感じとったせいだろうか。 まるで彼の緊張が伝わったかのようにおそるおそる瞼を開けたガーネットだったが、その視界の両側を覆っていたものに黒真珠にも似た瞳を驚きに見開く。 彼女の長い黒絹の髪と細い背を覆うかのようなそれは、複雑かつ繊細な意匠を凝らしたレースで縁取りされていた。よく見ると小花を散らした図柄が意匠化されており、それがつながって一続きの模様になっ ている。その模様には技巧を凝らしてあったものの、そのもの自体には色がなかった。いや、色などつける必要のないものなのだ。 「白が似合うのはわかっていたから多分大丈夫だろうと思ってたけど、やっぱり似合うよな。…よかった」 目の前でそう言って笑うジタンの笑顔は、照れ隠しとそれでも隠しきれない嬉しさが半々に同居していた。 驚きの方が先に立ってしまって他の感情が追いつかず、呆然と言葉もないままガーネットはそっと指先でそのレースに触れた。そしてそれが彼女の頭から背中を緩やかに覆っているのを確認して、やっとのこ とでかすれた声で言葉を紡ぐ。 「ジタン、これ…」 それ以上の言葉を紡ぐことは出来なかったし、その必要もなかった。 一度こぼれかけた涙がまたその瞳の端に浮いてくると、泣かなくてもいいのにと言いながらジタンの指がそれをぬぐった。 「誰からも祝ってもらえないけど、願い事はかなえることができるから。――だから」 二人だけでも、いいよな?と小声で呟いたジタンに、とうとうガーネットは答えることが出来なかった。ただ、こくりと首を縦に振った時にこぼれてしまったのを境に後から後から頬を伝う涙をぬぐうのが精一杯で、とうとう顔を両手で覆って泣き出してしまった時には心底慌てたジタンが腕の中で時間をかけてなだめたのだった。 やっとのことで落ち着いたのだが赤い目元が恥ずかしいのかうつむいてしまうガーネットの両手を取り、その小さな両手を軽く上下に揺さぶってまるで小さな子供をあやすようにしながら、ジタンは軽く彼女の唇を盗んでみたりして笑っていた。 その笑顔が、普段の子供のような雰囲気と同時にどこか大人びた印象を持っていたのを、後々ガーネットはよく思い出すようになる。 白い両手を軽く握っていたジタンは彼女の左手を自分の右手で取ったまま、自然な動作で左手を傍らに伸ばした。そこには、いつの間にか精巧な彫りを施した小さな木の箱があった。 まだ赤い目を不思議そうに見張るガーネットの前で、ジタンはその箱を器用に片手で開けた。留め金がはずれる小さな音と箱の蓋がきしむかすかな音の後に見えたものに、彼女は彼とその箱の中にある物の間 で忙しく視線を往復させた。 「見つけたのは外側の大陸なんだけど、加工して仕上げてもらうのにトレノまで行ったから帰ってくるのが遅くなったんだ。せっかくトレノまで回り道したんだから、じゃあって思ってそのベールも選んだんだ けど」 箱の中で黒のビロードの上に大切そうに置かれているそれらの一方を手にしたジタンは、まるで壊れ物を扱うかのように彼女の左手を取ったまま、いいかな?と独り言のように呟いた。 それは、水晶にも似た輝きを放つ小さな赤い宝石の指輪。台座の色は肌に馴染むことを考慮したのか金に近い色調をいくらかおさえ気味にしてあり、赤い石を支えるように二回りほど小さな小粒の真珠が光っ ていた。 潤んだ黒真珠の瞳が幾度か瞬きをし、純白のベールが彼女が首を縦に振る仕草に合わせてふわりとやわらかく揺れるのを承諾と見て取って、彼は真剣さと敬虔さをこめた表情のまま誓いの印をその細い指に滑 らせる。 「…気にいった?」 「気に入っただなんて、そんな言葉じゃ足りないわ」 ほら、また泣く、とジタンが言うのでやっとのことで涙をこらえたガーネットに、彼は箱の中に残っていたもう一方の印を手のひらに取って彼女に示す。 彼の手のひらの上で光ったのは、蒼い石の一組のピアス。彼の髪の色に合わせたかのような色の台座とその瞳の色によく似た蒼い石がガーネットの瞳に映りこんでいた。 細い指先でそれをそっと取って、彼の意をあやまたず汲み取ったガーネットは膝立ちになると彼の耳に指を伸ばす。彼女の指が耳に触れた時、ジタンは静かに瞳を閉じた。かすかに震える指先は思うように動 かないらしく長い時間がかかったが、ジタンは無言で瞼を降ろしたままだった。 「大丈夫?痛くなかった?」 元の位置に座りながらそっと彼の耳に触れるガーネットの手を握り止めながら、ジタンは彼女の左手を自分の手で包み込んだまま笑った。 「この二つの石、同じ石なんだよ」 「え?」 「ごく稀にだけど、一つの宝石の原石に違う色が混ざっていることがあるんだ。これもそんな珍しい石で、一つの原石のちょうど右半分が赤で左半分が青だったんだ」 ――だから、ずっと一緒にいることを誓うにはちょうどいいと思って。 その言葉の後半がジタンの口から紡がれる途中で、ジャスミンの香りをまとった彼女の華奢な体が彼の腕に飛び込んでくる。 その香りにこめられた願いを確かに受け取って、ジタンは彼女と同じことを願い、そして彼女の願いをかなえることをその心の内で静かに誓った。 |
| 汗ばんだ彼の髪をそっとかきあげた時、二つの石が光をこぼした。
彼女の左手の指の赤い石と彼の耳の蒼い石が、わずかな月光を反射してまるで共鳴し合うようにさやかにきらめく。 表裏一体のような二つの世界――テラとガイア――の申し子のような自分たち。 テラの月のかけらのような石を彼女に、ガイアの月のかけらのような石を自分にと選んだ彼の心を触れあった温もりから感じとって、ガーネットは視界が涙でにじんでいくのを止められなかった。その涙のわけは、胸を満たすたとえようもない幸福。 目尻からこぼれ続ける涙が二つの石の輝きを幾重にも重ね、赤と蒼の光が溶け合うようにすら見える。 …まだ、ずっとそばにいることは出来ないけど、いつでもどこでも想っているから。 幾度か重なった唇の間で囁かれた言葉を、どんなにか待っていただろう。 何よりも誰よりも、今一番大切な互いの命を受けた場所を象徴するかのような二つの石がすぐ近くで輝いているその光景に、こみあげてくるいとおしさの分だけまた涙がシーツの上に広がった髪の上に落ちる。 幾度涙をぬぐってもいくらなだめても泣きやむ事が出来ない彼女に、困ったようなそれでいてどこか嬉しそうな表情になると、ジタンはありったけの優しさとその想いをその腕にこめるように白く華奢な肢体 を抱きしめた。 同じ石を共に誓いの印とし、そして持ちうる全ての心を互いに与えるべく、重なる肌の温もりに溺れてしまうくらいになりながら。 離れていても、誓いの石を通して通い合う心を確かめながら。 |
| ――小さな誓いの儀式を見守ったのは、孤独な暗い夜空に浮かぶ二つの月だけ。
悠久の時の流れの中で、星と大地を見守ってきた二つの月は二つの世界の申し子たちだけの誓いをも静かに見守る。 しかし見守るだけの月が知っていることがある。 それは、この夜が明ければ、時には互いの手を取り、時には道をたがえながらも彼らが共にその道を歩んでいくということ。 椅子の背に丁寧にかけられた花嫁のベールがかすかな夜風に揺れた。 祝福なき申し子たちのための、大地や星たちの声なき祝福であるかのように。 |
 |
| あとがき | |
| ‖まにまに文庫‖ | ‖石鹸工場‖ |