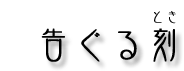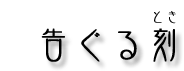|
|
人の誕生を夜明けに、その死を日没に例えるのはそう珍しいことではない。
その太陽の運行に人の一生を重ねることを最初に言い出したのは一体誰だったのか、今となってはもう知る術すらないけれど、一つ言えることがある。夏の日が長く大地を照らすように、冬の日がほんの一時大地を薄日で照らすような、そんな日もあるのだと。
同じものに例えられても、その長さには歴然とした差が存在するのだ。
それを定める者を神といい、創造主と言うのだろうと思う。
――でも、俺は生きている。
まだ太陽は地平線の近くにあるのか、部屋に差し込む光は淡く目覚めたばかりの目には優しいほど。
長旅の疲労感はとうに消え、残っているのは心地よい気だるさとかすかな温もり。
まだ眠気を引きずってはっきりとはしない意識のまま、ジタンは左腕を動かした。いつもならこんな早朝にはまだ眠りの園の中にいる彼女が規則正しい寝息をたてていて、その体を抱きなおしてもう一度寝なおすか、もしくはそのまま抱き込んで目が覚めるまでじっと寝顔を見るのが習慣になっている。
しかし、動かした左腕は慣れない軽さに空を切った。
おや、と思い腕だけでなく首ごと左肩の上を見ると、そこにあったのは空のシーツだけ。まだかすかに温もりを宿したそれから、彼女がそこを離れてからまだ間もないことがわかる。いつもなら彼の方が先に目覚めるはずなのに、その日に限って彼女の方が先に起きたらしい。
肩にかかる髪をわずらわしげにかきあげてジタンが体を起こした時、かたりという物音がした。
振り返ったそこで舞っていたのは、早朝の涼しげな微風に揺れるカーテン。テラスへと続く大きな窓にかかったそれの間に、朝の白い光を輪郭とした人影があった。
もう見慣れているはずなのに、視線ごと捕らわれてしまったかのように目が離せなくなる。
逆光になってしまっているせいではっきりとはせず、輪郭のみを朝の光に浮き上がらせたかのような姿。華奢な体の線がかえって際立つようなそんな影が、レースのカーテンをくぐり抜けた時を境に影でなくなる。まるでレースの扉をくぐって違う世界から戻ってきたかのように、室内に入った姿が色と質感を伴ってはっきりとした。
まだ光をまとっているかのように艶やかな髪がかすかな風に揺れる。黒絹の髪と白い薄絹の夜着、そして陶器にも似た白さの肌という対照的な色の中に、淡い色の花々が一際鮮やかに目に飛び込んでくる。早朝はまだ肌寒いというのに薄手の夜着一枚のままで外に出ていたらしく、彼女は腕に色とりどりの花を抱えていた。その優しい色と同じように優しい香りがふわりと風にのって漂う。
夜着の裾を少し持ち上げるようにして部屋に入ってきた彼女は寝台の上の彼を見て、そしてけぶるような微笑みを浮かべた。
それは、天上の世界からふいに彼の前に精霊が舞い降りたかのような光景。
「おはよう、ジタン。もう目は覚めていて?」
|
|
花をこよなく愛する女王のために整えられた庭園は、小鳥のさえずりと朝のやわらかな光だけで満たされた世界だった。春を謳歌する花々の間をそぞろ歩きながら、彼女の指は時折淡い色と香りの花を摘み取って腕に抱えている。
閑雅で静謐な空気は早朝にしかないものだけれど、彼女の心にほんの少し影を落としているものがあった。それは、夕べ帰ってきた彼の様子ゆえ。
――おかえりなさいという喜びと出迎えの言葉を言う暇もなく、一晩中愛された。
夜の余韻を留めたままの体を静謐な夜明けの空気にさらしてしまうことは場違いに思えるほどだったけれど、出来るだけ静かに彼の腕を抜け出してテラスから庭園に降りた。
本当なら、いまだ体のそこかしこに響く余韻に浸りながら彼の腕の中でこの静かな時を心ゆくまで過ごしてみたかった。普段より幼くなる彼の寝顔を見る機会などそうあることではないし、何よりその時間は彼が先に目覚めないという幸運に恵まれないと過ごせないもの。
けれど、ガーネットはその腕を抜け出して今花を摘んでいる。
優しい淡い色合いの花、穏やかな香りの花を選びながら、その繊手で一輪一輪花を摘み、腕に抱える。
それは、彼が目覚めた時のための儀式めいたもの。
夕べ、ふと深夜に目覚めた時になにげなく見てしまった光景を、ガーネットはそのまま眠りの園に引きずりこまれながらも夢だとは思うことが出来なかった。
そしてその光景を目にしたことを思い出すと、普段通りに彼に接することが出来ないような気がした。だから、彼が目覚めないうちにその腕を抜け出し、花を摘んでいる。
この花々のように優しい笑顔で、目覚めた彼の目に最初に映るように。
何気なく白く小さな薔薇を手折ろうとした時、ふいに小さな痛みが指先に走る。咄嗟に茎から離してしまった指には、血こそ出ていなかったものの小さく赤い点が刻まれていた。
その指先をぼんやりと見つめ、ガーネットは顔をあげた。
その視線の先で、白いカーテンが揺れている。先ほど出た時に開け放したままにした窓のカーテンが、早朝の微風に揺れていた。
まるで招かれるように、彼女はふらりと歩き出した。色とりどりの花束を抱えてそのレースのカーテンをくぐり、まだ薄暗い室内へ入った時、外の明るさに慣れた目が室内を見渡せるようになるのに少し時間がかかった。
開けておいた天蓋の紗のカーテンの向こうに、体を起こしている人影を彼女は見つける。
そして、出来る限り優しい声と笑顔で言葉を紡ぐ。
「おはよう、ジタン。目は覚めていて?」 |
 |
――もう、わかっているんでしょう?
彼女との関係を一言で表すとするなら、妹とでも言えばいいのだろうか。ジタンの後に生み出された、同じジェノムである彼女。しかし、妹という言葉からは想像しがたい関係であることは確かである。それは、彼女が感情というものを排除されて生まれたいわば典型的なジェノムであり、彼の方が予測しがたい成長過程を経たということにも起因する。
楽観的な思考や予測の一切を排した妹の冷静な声が容赦なく彼の背中に届く。
同じ道を生きるなんて出来ないかもしれないのよ。確かにあなたはこのガイアで育ったことといい、ガーランドがあなたに感情があるのを是としたことといい、私やクジャとは違うわ。不確定な要素も多すぎる。…でも!
妹の声に珍しく感情の色らしきものがあるのを、ジタンは不思議な思いで耳にしていた。
私たちは、もう命の猶予すら定められているのかもしれない。それを、彼女にいつ言うの?いつかきっと彼女がそれを知る日が来るのでしょう?その時にあなたは…。
どうするの?とおそらくは続けようとした妹の言葉を遮るように、彼は本心からの言葉を口にした。
その俺の命を、ここに引き戻してくれたのはガーネットなんだ。だから、俺はあいつのところに帰った。
薄々とはわかっていたことだったが、同じジェノムであるミコトの言葉で明確な形となって突きつけられたその可能性に平静でいられるはずがなかった。
後悔するわ、絶対に。あなたも、彼女も。
そんなことはない、と否定することは出来なかった。妹の言葉を背中に受けながら、ジタンは黙ってアレクサンドリアへの帰途についた。
彼女の顔を見たら、笑いながらただいまと言えばいいのだと自分で自分に言い聞かせながらの道中だったのに、いざ彼女の顔を見たらそんなことは跡形もなく脳裏から消えていた。
何も知らず、彼の顔を見た途端嬉しげな笑みで顔をほころばせる彼女をそのまま抱き寄せて、時も忘れてその肌の感触と熱と声を独占した。
抗うことすら許さず。
その細い脚の爪先から乱れた髪の先まで覚えこむように。
彼女の五感の全てを彼自身で埋め尽くしてしまうかのように。
その激しさの理由を、彼女は問おうとはしなかった。ただ、何が彼の上に起こったのかと不安げな色を瞳に浮かべながら、力など入るはずのない両腕で彼を抱きしめようとしただけ。
引きずりこまれるように眠りに落ちてしまった彼女が、そうやって待つことをいつしか覚えていたことに改めて気がつきながら、ジタンもまた腕の中の温もりを離すまいとしながら眠ってしまった。
「ゆっくり眠れたかしら?もう一眠りしてもいいのよ。まだ朝も早いし、起こさないように皆には言っておくから」
朝の光をまとったかのような清楚な雰囲気の彼女からは、夕べのことなどまるで感じ取る事は出来ない。けれども、自分が求めた分だけ理由も聞かずにすがってきた記憶と感触は、彼の脳裏と体にまるで焼きついたかのように残っている。
腕に抱えた花のような彼女のその微笑みが、まるで鋭い切っ先のような鋭利さで彼の心に突き刺さる。
自分の道は自分で切り開くもの。
そう信じて疑いもしていなかった自分の命の猶予が他の者に定められているのかもしれない。それがたとえ自分の創造主であっても到底受け入れることなど出来るはずもない。しかも、それはもう一つの耐えがたい未来を彼にいとも容易く思い起こさせる。
彼ゆえに待つことを覚えてしまった彼女を、まだ何も知らない彼女を、変わらず微笑んでいる彼女を、この上おいて逝かねばならないのかもしれないという未来を。
|
|
私、上手く笑えているかしら?
彼が目覚めたらすぐに聞きたいことは山とあったけれど、それを全て胸の奥に封じ込めたまま彼女は穏やかに笑うように努めていた。彼に何があったのか知りたいと思う気持ちを、まるで胸に抱えた花々で覆い隠してしまうかのように。
「ゆっくり眠れたかしら?もう一眠りしてもいいのよ。まだ朝も早いし、起こさないように皆には言っておくから」
まだどこかぼんやりとした瞳で寝台の脇に立つ彼女を見上げるジタンに、場をつなぐかのようにガーネットが声をかけた時、朝陽にきらりと光る物が見えた。
その光景に、鼓動すら止まるような思いに駆られて、ガーネットは立ちすくんだまま彼を見つめる。
海と空のあわいのような不思議な色の瞳から、透明なしずくが二度三度と頬を伝ってこぼれ落ちるその光景に、彼女は時を忘れて立ちすくむ。
「…ジタン?」
戸惑いがちな彼女の声に、彼は急にはっとしたような表情になった。そして、自分の頬に伝わるものに触れて、半ば呆然とする。まるで、意識しないまま泣いたのだと言うかのように。
「…俺」
言葉を紡ごうとするジタンのその声より前に、ガーネットはとっさに彼に背を向けた。腕に抱えていた花を壁際のサイドボードに置きながら、彼女は殊更明るい声で言った。
「まだ肌寒いけど綺麗に咲いている花がたくさんあったの。後でちゃんと生けるわ。そうね、せっかくだから朝食の後のお茶の時間をゆっくりとりましょうよ。花を眺めながらなんていいでしょう?」
声が震えてしまわないようにするのが精一杯で、まともにジタンの顔が見れなかった。
夕べ、ふと目を覚ました真夜中に見たのは、眠るジタンの伏せた瞼の端から涙がこぼれるその光景。
――何があったの?そんなに悲しくて辛いことがあったの?
一晩中愛して愛されて、それでもまだ癒しきれない傷を負っている彼にどんな言葉をかけていいのかわからないまま、ガーネットは彼に背を向けてしまった。それは、彼がどんな苦境にあっても立ち上がる姿をよく覚えているから。その彼が意識せずに泣くほどの何かがあったことに、少なからず彼女も動揺したから。
大事な人だから、それだけにかける言葉を見つけられない彼女の背を、慣れ親しんだ温もりが覆ったのはその時。 |
|
彼女がいたからこそ、彼は生の世界へと生還することが出来た。
自分の意志以外によって命の猶予が定められているかもしれず、生と死の狭間にある自らを強く意識したその時に目にした彼女の姿は、例えようもなく美しくて、そして事実を告げることがどんなに残酷なことか思い知るのに十分で。
神の御手によるようなその姿を悲しみで曇らせることなど出来るはずがなかった。
だから、背を向けた彼女をその背後から抱きしめた。
神の御手によって彼の前に舞い降りたかのような彼女を腕に、自らの創造主によって定められたかもしれない命の猶予を感じながら。
「…ああ、綺麗だな。でも、どうせならもっと俺の側で寝てればよかったのに」
背を向けた彼女が涙に気がつかなかったことを祈りながら、ジタンはその温もりを抱きしめる。 |
|
告げられない彼と、尋ねられない彼女との間にこの時生じた隙間が埋まるのは、さらに時を待たねばならない事を知るのは、この世の者ならぬ神のみであった。 |