
 |
| 俺が、お前の目と耳になるよ。
知ってるか?『ガーネット』の石は、昔は戦場に出る戦士たちの護りの石だったんだ。このアレクサンドリアの王女だったお前が、その名前だってことは、多分国の護りになるようにっていう願いがこめられているんだろうな。 わかってる。お前はこの国を捨てきれない。いろいろあったけど、この国はお前を必要としていて、そしてお前にとってもこの国は大事なものだから。いくら復興したからって、中途半端なままで投げ出すことなんて出来ないだろう? それなら、俺はお前の代わりに世界を見てくるよ。 そしてそのありのままをお前に伝えよう。 …その代わり。 帰ってきたら、あの歌を歌ってくれ。そうすれば、俺は絶対ここに帰ってくるから。 |
|
離れていた年月の間に伸びた背丈。 逞しくなった体と、どこか精悍さを帯びた真面目な顔。でも、笑うとあの頃のままの笑顔。 変わらないようでいて変わったその面影のわけは、逝ってしまった小さな大切な仲間のことがあったから。 誰もいない夜更けに、静かに伝えてくれたその最期の言葉は、同じくらい静かに私の胸に響いた。 そして、その最期の様を聞いて泣き出した私を、あなたはただ抱きしめていた。 もう泣いてもあの子は帰ってこないけれど。その時の私は泣くことしか出来なかったの。わかっていたことだったけど、やっぱり、泣くしか出来なかった。 あなたがもう生きてはいないだろうと思った時も、誰もいないところで一人で泣いたの。泣いてばかりでは何もならないとわかっていたけど、どうしようもなく涙が溢れてきたから。泣いて、泣いて、涙が枯れた頃、やっと顔を上げる勇気が出てきた。 あの時は一人だった。でも、今はあなたがいる。 記憶も悲しみも全部共有出来るあなたに包まれて、やっとあなたが帰ってきてくれたんだって実感できた。 あなたが私の所に帰ってきてくれたように、いつか私があなたの所にいけるように、その日までのお守りに、私は私と同じ名前の石をあなたに手渡した。 あなたを守ってくれますように。 そして何度でも帰ってきてくれますように。 世界の果てでも、あなたの側に私がいると思えるように。 |
|
木々の葉ずれの音が月夜のしじまに密やかな囁きとなって流れる時刻に、その男は愛用の大剣を地面に垂直についてその柄を両手で握り、仁王立ちとなって静かに瞑目していた。 蒼い蒼い月が銀の光を音もなく地上に降り注ぐそんな夜には不似合いなほど、研ぎ澄まされた空気が張り詰める。その銀の月光がふと雲間に隠れた刹那。 闇に閉ざされた中で何か影のようなものが揺らめいた。暗闇の一部を切り取ったかのような忍びやかなその揺らめきが身軽に舞い降りたその瞬間、鋭い音が夜のしじまに響いた。鍛え上げ、磨き上げた大剣のその鋭い鞘走りの音は風の囁きを圧してあまりあった。 雲に遮られてわずかになった月光を反射してその刀身が鈍く光り、絶妙の呼吸で舞い降りた影をなぎ払う。 …否。 一条の光となった刀身は影があった場所の空を切るのみだった。ち、という舌打ちの音とほぼ同時に、刀身をかわした影が空中で見事に一回転し、わずかに離れた地面にただの一度もよろけることなく降り立つ。その影が降り立った瞬間のわずかな間のうちに、男は一気に間合いを詰めた。 大上段に振りかぶった渾身の一撃が影を真っ二つにしようとしたその時、耳をきしませるような音と共に火花が散った。 振り降ろされた大剣を受け止めているのは、交差された二本のダガーだった。力と力の均衡がどれほど続いたのか、ふいに影が口を開いた。 「…おい、おっさん」 それが合図だったかのように、均衡が解けた。 雲に顔を隠していた月が息詰まる対峙が終わったのを見届けたかのようにまた地上を照らし出す。 互いの愛用の武器を下ろし、向き合った影と男はそれぞれ異なる表情を浮かべていた。 男の表情は、苦虫を噛み潰したとはまさにこのことと言わんばかり。少々時代ががって見えるほどの甲冑に身を包み、一目で業物とわかる大剣をどこかいらついた手つきで鞘に収める。不器用な忠義一辺倒の騎士、というのがいかにもわかる風体と顔つきである。 一方の影の表情は、どこか楽しんでいるような風情であった。大剣の一撃を受け止めてしびれているはずの腕を悟られないようにいとも軽々とダガーを手の中で回してみる。少年の面影をまだどこかに残した体格だが、俊敏さをそのまま形にしたかのようなしなやかさがある。 「いつも思うんだがな、俺は愛しい女の元に帰ろうとする時にどうしておっさんみたいなむさい奴の相手をしないといけないんだ?」 彼の癖である、筋肉をほぐすかのように両肩を回すその仕草が張りつめていた緊張感までいとも簡単にほぐす。 「その言葉、貴様にそっくり返してやる!貴様がこんな夜更けにしか帰らんおかげでな、見ろ!」 男は自分の背後を示した。そこには、男と影が立っている庭――王宮の中でも一際奥まった奥宮の庭――に面したテラスがあって、そのテラスと部屋の境の大きなガラス戸の内側にかかった白いカーテンがふわりふわりと揺れていた。 「風の便りでもなんでも、お前が帰ってくると聞いたら陛下は絶対に窓を閉めようとなさらない!自分をはじめとする王宮騎士が日夜詰めて万全の警備体制を敷いているとはいえ、御身の大切さを思えば是非ともふらちな輩が万が一にも忍びこまないようにと幾度も幾度もご注意申し上げたというに!」 「それでおっさんがこの夜更けに無粋な見張り役なんぞやってるわけか」 「だいたいだな、王宮が性に合わないだとかぬかして、陛下のご寝所にこんな夜更けに忍びこむとは何事だ!やましい所がなければ堂々と昼日中に王宮の正門をくぐればよかろう!」 に、と影が笑う。 「わかってないなあ、おっさん。こうやって忍び込むっていうのがいいんだよ。それに、あんなに大勢の人間にがやがや囲まれてちゃ、あいつだって素直になれやしない」 男の仕えるただ一人の人間をあっさりと『あいつ』呼ばわりすることは、どうやら男の許容範囲だったらしい。なおも何か言おうとする男を遮って、快活そのものの声がこう言った。 「俺もやっとのことで長旅から帰ってきたんだからさ、いいかげん通してくれよ」 通してくれと言いながらあっさりとテラスの階段を上り、ふとジタンは振り返った。月の光を受けて、その金色の髪が露になる。 「新婚早々夜勤続きで悪かったな、奥さんによろしく」 スタイナーの返事を聞くより前にジタンは背を向けた。スタイナーの反応なんてわかりきっているから見なくてもいいくらいだ。真っ赤になった後、照れをごまかすように何も言わないで憤然とした様で帰っていく忠実な王宮騎士がよくわかって、ジタンは思わず笑みをもらす。 ジタンが笑みをもらしたその時、憤然と早足で立ち去っていたスタイナーはふと自分の両手を見た。 「…あやつめ、また腕をあげおって」 スタイナーの呟きから遅れること数瞬、ふわふわと風に舞うカーテンをくぐろうとしたジタンもまた軽い痺れの残る手のひらと腕を見た。 「…あんの馬鹿力。思いっきり打ちこんできやがった」 |
|
もう駄目かとも思った。これで最期なのだと何度も何度も思って、不思議と気持ちが穏やかになった。その生と死の瀬戸際に、ふと音も動きもない時間がほんの一時あった。 その時、なぜか、生き延びようとあらがったわけでもなく、死を見つめて諦観したわけでもなく、何も思わない心の底から、あの歌が口をついて出てきた。 それが、奇跡の始まり。 生きて戻って、彼女の元にたどり着くまでには、彼女の声でこの歌を再び聞くまでは、決してこの世界から離れてなるものかと、拳を握り締めた。 元々はこの世界の者ではなかった。むしろ、この世界を破滅へと導く先導として偽りにも近い生を受け、幾つもの偶然と必然と、そして時には迷いながら行く手の道を選んだ自分の意志とを道標に駆け抜けてきた。特に何か目指すものがあったわけでもなかったその日々の刻が、一つの出会いをきっかけとして加速度を増した。 どうして帰ってこれたの?とどこか幼さを残したままの瞳で見上げてくる彼女に、あの歌を歌ったんだ、と答えたのは、ごまかしでもなんでもなく、本当のことだったから。生と死のぴんと張り詰めた境界線を渡るようなあの刹那の時の連続だった時間を、その時彼女に話すのはやめようと思った。 奇跡をもたらしたのは、彼女の歌だったのだから。いつか時が過ぎて、あの一瞬のようだった戦いの日々を懐かしく振り返った時に、逝ってしまった一人の仲間の意思を成し遂げたと思えたその時に、話せばいいことだと思ったから。 今は、互いの命の鼓動を聞いていればいいと思ったから。 彼にとっての奇跡の源の少女は、あどけない表情で眠っている。起こさないままだと、朝目が覚めた時に、どうして起こしてくれなかったの?!と怒られてしまうのだが、それをなだめるのもすっかりコツを覚えてしまった。 天蓋から降りる薄い絹のカーテンを音もなくくぐってベッドの脇に立った時、にゃあとか細い声がした。 「…しっ。静かにな、ジタン」 シーツの上に散る長い黒髪をしとねにした小さな子猫が深夜の来訪者にわずかな警戒の声をあげる。金色に近い毛並の小さな体の首についた赤い石がわずかな月明かりに光った。 ジタンがたまたま城下で見つけて拾ってきた子猫を、ガーネットは殊のほかかわいがった。ガーネットの石の首輪をつけ、何故か『ジタン』と名前を付けて。アレクサンドリアの女王陛下の膝を独占する子猫の首を掴んで、ジタンはその高貴な子猫を手近な椅子の上のクッションの上にぽんと放るとこう言った。 「ジタン、俺がいない間の任務ご苦労さん。当分俺がこいつの面倒見るから、ゆっくりしろ」 了解、と言わんばかりに子猫がクッションの上で丸くなるのを見届けて、ジタンはそっとすべらかな褥に滑り込んだ。 長い黒髪が散るシーツの上に極力静かに体を横たえると、すぐ近くで規則正しい寝息が聞こえた。 月明かりに浮かぶ白皙の肌と薄紅の唇。対照的なほど夜闇の色をした長い髪。焚きしめられた香の匂いが懐かしいほどで。今は眠りの妖精が伏せてしまっているその瞳が少し残念といえば残念だが、きっと夜が明ければ自分を映してくれるはずのもの。 「…ただいま、ガーネット」 額に落とした唇のぬくもりを感じてか、喉の奥に絡まるような声が細い喉から漏れた。起こしたかとひやりとするジタンの隣で、眠りの園にたゆたったままの彼女がふと笑みをこぼした。 …いや、ほんとは起こして久々の再会の熱い抱擁なんかが欲しいんだけど。 その笑顔があんまりにも穏やかで無邪気なものだったから、ジタンは自分の考えが急に恥ずかしいやらやましく思えてくるやらでしばらく焦った。 まあ、そういうのは明日の朝でもいいし。 細心の注意を払ってガーネットの体を抱きこむと、その香の匂いにふいに眠気が降りてくる。慣れたものとはいえ今回のように長旅となるとさすがに疲れも気がつかないうちにたまっている。それでもジタンはここ以外の場所で羽を安める気はない。 ふわあとあくびを一つかみ殺して、ジタンは霞ががってくる意識と視界の片隅でいつものように思う。 明日の朝はガーネットより早く起きておかないとな。ガーネットが一番に見るのは俺でなくちゃいけないんだから…。 |
|
かたん、と閉め忘れた窓が夜明け近くのわずかな風に揺れた。 東の空がほの白く染まり、じきに太陽が大陸を照らし出す。 大陸に生きる者全てに朝が訪れる。何物にも遮られることのない、陽の恵みがやわらかな光となって降り注ぐ。 ――霧はもう、そこにはない。 | |
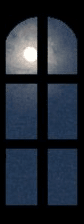 |
| あとがき | |
| ‖まにまに文庫‖ | ‖石鹸工場‖ |