
|
 |
| 作 まよ |
開け放たれた窓からは、初夏の微風が絶えず吹き込み、薄いカーテンを揺らしている。
|
魔女イデアとその騎士、サイファーと戦った後、魔女イデア―――まま先生に掛けられていた呪縛は解き放たれた。
|
しかし、その代わりに。 |
リノアが、動かなくなった。 |
最初の内は、眠っているだけかと思った。
|
―――何だよ、それ。
|
『絶望』。 |
その時仲間達の顔に、無意識に避けていたであろうこの二文字が表れた。
|
しかし、俺は信じない。 |
あのリノアが。
|
起きろよ、リノア……… |
(……え…ちゃん……) |
いくらこうして傍に居ても、この耳には、リノアの声が届かない。
|
あんたと初めて会ったのは、…確か、SeeD就任パーティーだったな。
|
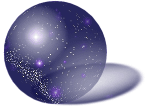 |
―――「君が一番カッコいいね!」
|
―――「やった~!SeeDが来てくれた~!
|
―――「カッコわるぅ~、命令に従う?それが仕事?」
|
―――「…やさしくない。やさしくない!!」
|
―――「素晴らしいリーダーね。いつも冷静な判断で仲間の希望を否定して楽しい?」
|
―――「だめだったの、一人じゃだめだったの。わたし、一人じゃ戦えなかったの」
|
―――「ミサイル基地でわたし、もう死んじゃうって思った。
そう思ったら、一番会いたかった」
|
―――「どうして?どうしてそういう言い方するの?
怒ってるの?ちょっと誤解があっただけだよね?」
|
―――「悪いってなんか思ってない癖に!もう話は終わりってことでしょ、それ。 どうしてこうなっちゃうのかな。どうしてなのかな!」 |
そうだったよな。
|
『わたしを見て!わたしに見せて!あなたの事が、もっともっと知りたいの!』 |
…正直、うざったかった。 |
周りの奴等も、俺がリノアとくっつく事を望んでいる素振りで、余計に頭が痛かった。
|
―――「わたし、戦うから」
|
レジスタンスに居ながらも、戦う事を回避しようとしていたリノア。
|
―――「スコール、助けてくれてありがとう!」
|
―――「聞きたい。スコールが考えてること、知りたいもの」
|
―――「行くぞ、スコール!」
|
そして。 |
―――「スコール! …リノアが!……リノアが!!」
|
(おねえちゃん…)
|
また、無くすのか…? |
(………エルおねえちゃん) |
俺は、―――子供の頃を、思い出す。 |
まだほんの4、5歳だった頃、俺は孤児院で暮らしていた。
|
俺は、待った。
|
―――信じた者に、捨てられる。 |
それは、無知で無力なガキの逆恨みだったのかもしれない。
|
『人は、独りだ。他人など、仲間など、俺はいらない。俺は独りでも生きていける』 |
情けないな。馬鹿みたいだ。
|
『どんな事があろうとも、決して俺から離れていかないものが欲しい』 |
リノアは、こんな俺でも、いつも引っ付いて来てくれていた。
|
もしも彼女がいなくなったら、……誰がこんな俺を必要としてくれる? |
誰が……? |
(ぼく……ひとりぼっちだよ) |
二度と、御免だ。 |
 |
どこまでも深く広がる空の茜が、目に染みる。
|
(俺のこと笑ってるかもな。いや、怒ってるかな?)
|
「俺、本当は他人にどう思われてるか気になって仕方ないんだ」
|
俺は、再びリノアの身体を背に背負う。
|
「スコール」 |
俺を求める声が聞きたい。 |
| あとがき | |
|
| |
| ∥まにまに文庫∥ | ∥石鹸工場∥ |